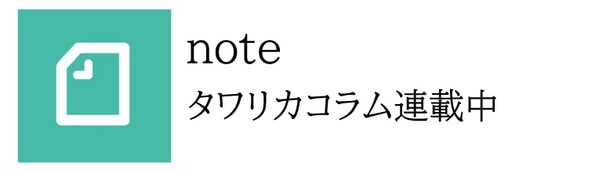栄養についての基礎知識①『炭水化物』と『脂質』について
健康な毎日を過ごすためには食べ物から取り入れた栄養素がカラダ作りの基本になります。食の力を味方につけて、カラダの内側から元気でキレイになりましょう。
1.食べ物の3つのはたらき
①体のエネルギーのもとになるもの:
●炭水化物(ごはん、麺、パン、いもなど)
●脂質(油、バター、ピーナッツなど)…バターや植物油などの油類には脂質が多く、これらは体を動かす力や熱のもとになります。
②体をつくるもとになるもの:
●タンパク質・ミネラル(魚、肉、豆腐、卵、チーズ、牛乳、ヨーグルトなど)…肉や魚、牛乳、小魚、海藻などに多く含まれているタンパク質やミネラルは、血液や筋肉、骨、内臓、髪の毛など私たちの体を作るもとになります。
③体の調子を整えるもとになるもの:
●ビタミン・ミネラル・食物繊維(野菜、果物)…野菜や果物にはビタミンやミネラル、食物繊維が多く含まれていて、体の調子を整えるもとになります。
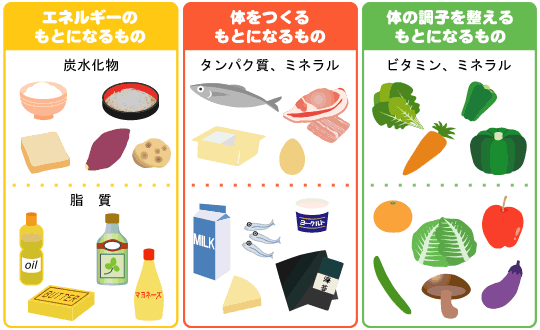
では、次から詳細を説明していきます。
2.炭水化物の特長(①体のエネルギーのもとになる)
*エネルギー源になる…脂質より消化・吸収が早く即効性があるので、脳のエネルギー源になるのは、飢餓状態にならない限りブドウ糖だけです。「朝食におにぎり説」の根拠ですね
*グリコーゲンとなる…エネルギーとして使われなかった血液中の余分なブドウ糖は、肝臓や筋肉でグリコーゲンに変化して貯蔵されます。
*中性脂肪となる…貯蔵しきれなかったブドウ糖やその他の糖類は、脂肪組織に運ばれ、中性脂肪に変えられて蓄積されます。
体内で炭水化物がエネルギーに変わる時には、ビタミンB1が必要です。炭水化物を摂る際は、ビタミンB1も一緒に摂ると効率よくエネルギー産生します。
炭水化物をとりすぎると⇒ 肥満、脂肪肝、虫歯、糖尿病になります。
炭水化物が不足すると⇒ 脳がエネルギー不足になる、肝臓の機能が低下、体内のタンパク質を分解してブドウ糖を合成しようとするので、やる気が起きない、疲れやすくなる、筋肉の減少、病気に対する抵抗力も弱まります。

3.脂質の特長(①体のエネルギーのもとになる)
*エネルギー源になる…脂質は体内で分解され1gあたり9kcalのエネルギー産生します。
*中性脂肪となる…増えすぎると肥満はもちろん動脈硬化などの生活習慣病の原因にも。
*体をつくるもとになる…脂質は細胞膜の構成成分にもなり、ホルモンや生理活性物質、神経組織の材料にもなっています。
*脂溶性ビタミンの吸収を助ける…脂溶性ビタミン(ビタミンA,D,E,K)を吸収しやくします。
脂質には 飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があります。 *飽和脂肪酸:(ラード、牛脂、バター、やし油、パーム油)…血中の中性脂肪やコレステロールを増やす。現代食では摂りすぎる傾向があるため摂取は控えたほうがいい。 *不飽和脂肪酸:(オリーブ油、菜種油、ごま油、レバー、えごま油、あまに油、さば、ぶり、うなぎなど)…血中コレステロールや中性脂肪を低下させたり、動脈硬化やがんなどの生活習慣病を予防する。 |

「②体をつくるもとになる/③体の調子を整えるもとになる」は次回ご紹介します。