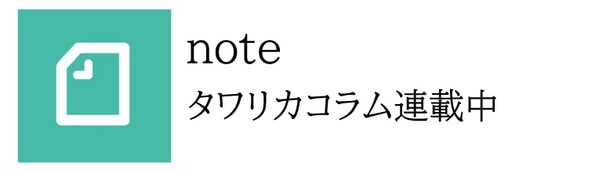栄養についての基礎知識②『タンパク質・ミネラル・ビタミン・食物繊維』
病気になった時が、当たり前と思っていた健康に感謝するときですよね。と、同時に、食べ物のことについて情報収集します。 今、口にするものが自分の体をつくる・活かすので、添加物などの毒を食べないようにしましょう。
1.タンパク質の特長(②体をつくるもとになる)
*体をつくるもとになる…私たちの体をつくる大切な栄養素です。皮膚、筋肉、臓器、血液、髪の毛、爪、骨などの構成成分になったり、ホルモンや酵素、神経伝達物質、抗体などの原料になります。
*エネルギー源になる…炭水化物が不足した時に、1g当り4kcalのエネルギーを供給します。
①タンパク質を多く含む食べ物
肉類、魚介類、卵、大豆、大豆製品、乳製品など
②タンパク質を多く摂りすぎると
*腎機能障害…タンパク質は炭水化物や脂質のように体内に蓄えることができないため、摂りすぎた成分は尿とともに体外に排泄されます。このため、摂りすぎが続くと尿を作っている腎臓に負担をかけてしまいます。
*骨粗しょう症…カルシウム排せつ量の増加のため骨量が減ってしまいます。
③タンパク質が不足すると
体力や免疫力の低下、脳卒中、成長障害に
タンパク質はアミノ酸がくっついてできています。アミノ酸は、動物性タンパク質、植物性タンパク質などさまざまな食材から摂ることが大切です。肉、魚介類、卵、乳製品などの動物性タンパク質には、必須アミノ酸(体内で合成することのできないアミノ酸)がバランスよく含まれています。穀類や豆類などの植物性タンパク質と合わせて摂取しましょう。
④必須アミノ酸
自然界には多くのアミノ酸が存在していますが、タンパク質の構成成分として利用されるのはわずか20種類しかなく、このうち9種類は体内で合成することができないので、食べ物から摂取しなければなりません。この9種類のアミノ酸を「必須アミノ酸」と呼びます。食べ物の中に必須アミノ酸が1つでも不足していると、タンパク質としての栄養的価値が下がります。
必須アミノ酸
|

2.ミネラルの特長(②体をつくるもとになる)
あらゆる物質を構成する基本単位を元素といいます。(つい先日、日本初の元素記号が発見されましたね!)自然界には100以上の元素が存在しています。人体の95%は酸素・炭素・水素・窒素の4つの元素で構成され、残りの5%の元素を栄養学では「ミネラル」と呼んでいます。
ミネラルは体の構成成分となり、微量ながらもビタミンと協力して体の調子を整える働きをします。微量で重要な働きをするところはビタミンと同じですが、ビタミンと異なることは体の構成成分にもなっているという点です。
ミネラルの主なはたらき
*骨、歯などの体の構成成分になる
*体液に溶けて、pH・浸透圧を調節する
*酵素の構成成分になる
*神経・筋肉の興奮性の調節を行う

必須ミネラル
人間に不可欠なミネラルは必須ミネラルとよばれ、現在16種類が知られています。
カルシウム・リン・カリウム・イオウ・塩素・ナトリウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・銅・ヨウ素・セレン・マンガン・モリブデン・クロム・コバルト
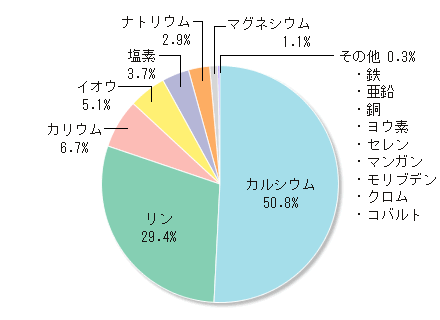
3.ビタミンの特長(③体の調子を整える)
ビタミンは体の機能を維持する微量栄養素です。3大栄養素のようにエネルギー源や体の構成成分にはなりませんが、3大栄養素が体内でエネルギーに変わる時や、筋肉や皮膚など体の構成成分に変わる時の手助けをする「潤滑油」のような働きをしています。
ビタミンは原則的に体内でつくることができないため、不足すると体に様々な影響を与えます。
また、血管や粘膜、皮膚、骨などの健康を保ち、新陳代謝を促す働きにも関与しています。
ビタミンは13種類ありますが、大きく分けて2つの性質に分かれます。

1.脂溶性ビタミン
*油脂に溶けやすい…油脂と一緒に摂ると吸収率はアップします。
*熱に比較的強い…ビタミンはそもそも熱に弱いですが、脂溶性ビタミンは熱に強い。
*摂りすぎは過剰症を引き起こす…体内(主に肝臓、脂肪組織)で貯蔵されるため多量に摂取すると頭痛や吐き気などの過剰症を引き起こします。過剰症は、肝臓などで貯蔵できなくなったビタミンがほかの必要をしない器官にまで流れてしまうことが原因です。
- 目のビタミン 『ビタミンA』
- 骨のビタミン 『ビタミンD』
- 若返りのビタミン 『ビタミンE』
- 血液のビタミン 『ビタミンK』
2.水溶性ビタミン
*水に溶けやすい…植物や動物の体内では水に溶けた状態で存在しています
*熱に弱い…とりわけビタミンCが弱く、火を加えるとビタミンが壊れてしまうのでそのまま食べましょう。料理には工夫が必要なビタミンです。
*過剰症の心配が少ない…余分な量は尿と一緒に排泄されるため。ただし、あまりに大量に摂取するとビタミンB2で知覚障害、ビタミンCで下痢などの危険性があります。
- 神経のビタミン『ビタミンB1』
- 発育・美容のビタミン『ビタミンB2』
- 肌のビタミン『ナイアシン』
- 女性のビタミン『ビタミンB6』
- 造血のビタミン『ビタミンB12』
- 妊婦のビタミン『葉酸』
- ダイエットのビタミン『パントテン酸』
- 髪のビタミン『ビチオン』
- 抗ストレスビタミン『ビタミンC』

4.食物繊維の特長(③体の調子を整える)
食物繊維は人の消化酵素で消化されない食べ物の成分をいいます。近年、有害物質の排せつや栄養素の吸収、腸内環境の正常化などの働きがあることが知られ、生活習慣病の予防と改善によいと注目されるようになりました。
水に溶けない不溶性食物繊維と水に溶ける水溶性食物繊維に分けられます。
①不溶性食物繊維の特長
▼食べ過ぎの防止
不溶性食物繊維の多い食品は、口の中でよくかむ必要があるので、早食いによる食べ過ぎを防ぐ効果があります。また、かむことによって、歯茎やあごを強化して歯並びをよくしたり、虫歯を防ぎます。さらに、消化されない性質があり、胃の中の滞在時間が長いため満腹感が得られます。
▼便秘の予防と改善
腸内細菌の分解を受けにくく、水分を吸収して何倍にも膨れ上がるために腸壁を刺激して腸の蠕動運動を促します。また、不溶性食物繊維を含んだ便は、水分を吸収して柔らかくボリュームがあるため排便がスムーズに行われます。
▼大腸がん予防
今や、女性の罹患率No.1は大腸がんです!大腸がんは欧米型の食生活の高タンパク質、高脂肪、低食物繊維で引き起こされる病気です。便の量が増えれば、腸内の発がん性物質の濃度が降下し、排便回数が増えることによって、発がん性物質が腸内に留まる時間が短くなります。さらに、有益な腸内細菌が増えることによって、発がん性物質の生成を抑制するなどの効果が期待されています。
▼有害物質の排せつを促進
排便促進効果によって、有害物質の体内滞留時間が短くなったり、吸着することによって排せつさせる作用もあるので、食べ物の残留農薬や食品添加物などにも効果があると考えられています。
▼不溶性植物繊維を多く含む食べ物
穀類、米ぬか、とうもろこし、ココア、豆類、いちご、野菜、きのこ、かに・エビの殻
②水溶性食物繊維の特長
▼糖尿病予防
水溶性食物繊維は、水分を取り込むことで粘度が高くなるため、胃から小腸への食べ物の移動が緩やかになります。また、ブドウ糖の吸収速度を緩やかにし、食後の急激な血糖値上昇を防いでくれます。これによって、血糖値上昇によるインスリンの分泌も抑えられ、インスリン不足による負担が減少します。
▼動脈硬化予防
水溶性食物繊維は、腸内でコレステロールを吸収する働きがあります。特に、ペクチンなど、ゲル状になりやすい食物繊維を摂取すると、便への胆汁酸の排せつ量を増やします。胆汁酸は、コレステロールを原料として作られるので、結果的に血中コレステロールを減らし、動脈硬化を予防することになります。
▼高血圧予防
腸内でナトリウムと結びついて、排せつを促すため、血圧を下げる効果があります。
▼有害物質の排除
スポンジのように水分を吸収してゲル状になり、余分な栄養素や有害物質を排せつします
▼便量増加作用
便の水分量を増やして柔らかさを保ち、便量を増加させて腸内の通過時間を短くします。
▼水溶性食物繊維を多く含む食べ物
りんご、かんきつ類、納豆、やまいも、おくら、海藻類、こんにゃく、アロエ、根菜類、こんぶ、わかめ、とろろ