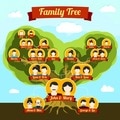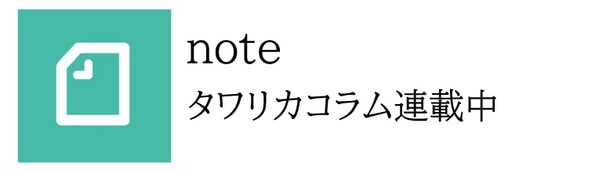とてもシンプルな “人生の法則”☆安岡正篤師のアフォリズムも少しご紹介
人生の法則、すなわち幸せの法則って、とてもシンプルなものだけれど、それを習得するのには長い長い時間が必要で… 人間学の大家といえば、最も有名なのが安岡正篤師。師のココロを磨くための言葉も少しご紹介します。
1.人生の法則
桃栗三年柿八年、柚子は九年で実を結ぶ。梅は酸いとて十三年。蜜柑大バカ二十年…即ち、二十年大バカになるほど、脇目もふらずに打ち込まないとモノにならないということ。継続は本気さの証明であり、本物は続き、続ければ本物になれる。
円覚寺 横田南領(なんれい)管長が師匠から絶えず言われ続けたこの言葉を心の基に、創刊して40年、藤尾社長(株式会社致知出版社)がそこで得た「人生の法則」とは。
十年で基礎工事
十年で得たのは、人間の花は十年後に咲く、ということ。
人間の花はすぐには咲かない。五、六年でも咲かない。こんなに努力しているのに、と途中で投げ出す人がいるが、それでは永遠に花は咲かない。
二十年で道の入り口に入る
二十年で得たのは、人生は投じたものしか返ってこない、ということ。
人生に何を投じたか、投じたものが自分に返ってくる。人前では健気に努力しているふりをしているが、人目がないところでは手を抜く。それも自分の人生に投じたものであり、そういう姿勢はその時はわからないが、後で必ず自分の人生に返ってくる。
三十年で道の風景が見えてくる
三十年で得た気づきは、人生は何をキャッチするか、キャッチするものの中身が人生を決める、ということ。
それは「感じる違い」であり、同じ話を聞いても、同じ体験をしても、キャッチするものの中身は人それぞれ。つまり、人生は受ける側の姿勢が常に問われている。
だから大切なのは、気づく人間になるということであり、気づけるためには求める心がなければならない。その、キャッチするものの質と量は、その人の真剣度に比例する。
四十年経ってわかること
四十年経って思うのは、道を創ってきたつもりが逆に、「道に歩ませてもらっていた」ということ。
四十年を経て思うのは、道は無窮である。道に終わり/限りはなく、人生これでいいということはない。一生不足不足と思ってつき進んで、死んだ後に見てはじめて成就できた、といえるものであるからこそ、生きている間は歩きつづけるものである。
|
人生の法則は常にシンプルだが、それを身につけるには一生を要する。 夢を実現させるために必要なのは、能力ではなく、真剣さの度合い。 真剣に継続して努力し続けることが、成功と失敗を分けるという秘訣。 |

2.人生の師:安岡正篤師のアフォリズム(格言・名言)
「忙人のための身心摂養法」
一. 心中常に喜神(きしん)を含むこと 二. 心中絶えず感謝の念を含むこと 三. 常に陰徳を志すこと |
喜神とは、どんなに苦しいことに遭っても心のどこか奥のほうに喜びを持つということ。
陰徳については、徳性というのは、人間の最も本質の部分であり、安岡教学の真髄ともいえる部分で、安岡師の言葉にあるように、
「人間である以上、最も大切なもの、それは徳性。先に求めるのは徳性であり、徳性があればそれらしき才智、芸能は後で必ず備わる。」
に代表されるように、人間としてまず志すのは徳性である。
また、安岡師が好んでおられたアフォリズムとして有名なのはこちら。
深沈厚重(しんちんこうじゅう) は是れ第一等の資質。 磊落豪雄(らいらくごうゆう) は是れ第二等の資質。 聡明弁才(そうめいべんさい) は是れ第三等の資質。 【どっしりと深く沈潜して厚み、重みがあるというのはこれは人間としての第一等の資質である。 大きな石がごろごろしているように線が太くて物事に拘らず、器量があるというのは第二等の資質である。 頭がよくて才があり、弁が立つというのは第三等の資質である。】 「呻吟語:中国明代のアフォリズムを呂新吾が自らの心を鼓舞するためにまとめた書物」より |
人間の品格
|
一. 高品 独行奇識(どっこうきしき)あるは高品という 【自由・自立にして俗物とは異なる。物事の是非、善悪を識別する知恵を持つ】 二. 正品 中をえらび執る有るは正品あり 【一定の知恵も見識もあり、中道というものを毅然と歩む】 三. 雑品 善有り過有るは雑品なり。勤徴(きんちょう)用うべし 【よいところもあれば過ちもある。このような人間は賞罰を行って用いる。】 四. 庸品 短無く長無きは庸品という。世用に益なし 【短所も長所もない人。これは世の中の役に立たない。】 五. 下品 邪と偽との二種は下品という。慎みて之を用いる無かれ 【心がひねくれて偽りの言動をする。こういう人間を用いてはいけない。】 |
人間の品性を五段階に分けて、明確に記述しているところは大変面白く、また現代にも通じる評価法のようにも思えます。やはり、下品な人というのは、最下層の人であるのですね。
もう一つ。安岡師のアフォリズムで有名な一文はこちら。
縁尋機妙 多逢聖因 (えんじんきみょう たほうしょういん) 普段からよい人、よい教え、よい書物などに縁を結んでおくことが勝縁、善縁になる。 でも、何が善縁になるのか、悪縁になるのかが凡眼ではなかなか見分けがつかないわけだから、 やはり日常から自分自身の心眼を磨く、人間を磨く努力が大切である、ということ。 |
3.あらゆるものに徳がある
「徳」とは、その人の内面に存在する「性」であって、生まれもって存在するものではない。
それは、生きていく中で、培われるものであり、光輝くような喜びや、楽しみや、善なること、また、腹立たしいことや苦しいこと、哀しいこと、つらいこともすべて含みこんで形成されたものが「徳性」。
つまり、資産や家柄、学歴など全く関係ない、ただ自分で創っていけるものであり、培ったもの。
だからこそ、その徳性が高い人物というのは、あらゆるものを超えてきたことの証であるから、誰にも真似できないパワーや尊厳や奇跡が備わっていることなのだ、
と、私は思います。