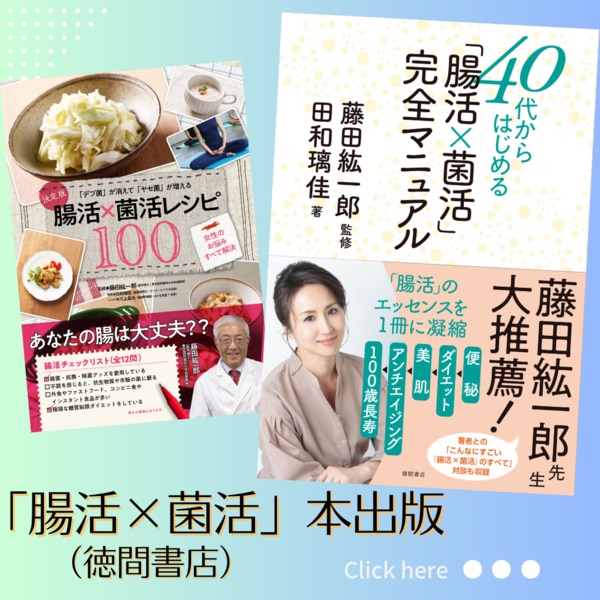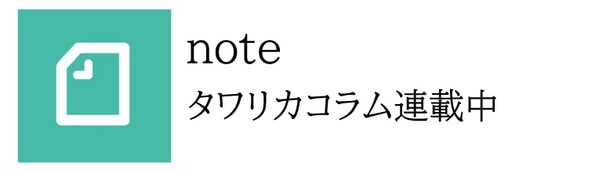二宮尊徳(二宮金次郎)の3つの名言|人生訓を大きく変える一言
背中に薪を背負った銅像で有名な二宮金次郎(尊徳)。 彼に対しては、勤勉なイメージだけだった私に、ある名言はまさに頂門の一針であり、その後、人生訓を大きく変える一言となりました。
その「ある名言」とは…
二宮尊徳(通称:二宮金次郎)
二宮尊徳(1787-1856)は江戸時代の農政家。600以上の疲弊した農村を復興させ、多くの農民・殿様を助けた功労者。本来は大財閥でも築けそうな実力と地位を築きつつも、私有財産を一切持たないまま亡くなるという本当に「無私の精神」をもち、実践された偉大な日本人です。
よく社長室に掲げてある(社長さんが好きな)「積小為大」という言葉は、二宮尊徳を代表する名言ですね。
この「積小為大(せきしょういだい)」という言葉の意味を、とても簡単に解釈すれば、 「塵も積もれば山となる」「千里の道も一歩から」といったことになると思いますが… 原文をご紹介するとこちらになります。
積小為大
大事をなさんと欲せば、小さなる事を、怠らず勤しむ(いそしむ)べし。
小積もりて大となればなり。凡そ小人の常、大なることを欲して、小なる事を怠り…
(中略)夫れ大は小の積んで大となる事を知らぬ故なり。
二宮尊徳「報徳記」より
小事の積み重ねと継続の大事さ、そして、その先にこそ大きな事を成せる【=積小為大】という意味です。
薪を背負った姿で有名な金次郎は、机上の学問を修めただけの学者ではなかったからこそ、死後160年を経た現代の私たちの心にもずしりと響くのだと思います。
七代目の子孫でいらっしゃる中桐万里子さん言によれば
- 金次郎は、世のため人のためというよりは、常に目の前の相手に応えようという感覚が強かったのではないか? 助けを求めてきた人たちの村や藩主に応えたい、そして、目の前の両親が頑張って育ててくれたことに応えたいという思いが強かったように思う。
とおっしゃっています。
心田を耕す
「あらゆる荒廃は心の荒蕪(こうぶ)から起こる」という言葉にも残したように
人の心の荒蕪、心田を耕すことですべてのものが豊かになる、と説いている金次郎。
人の心を田んぼに例えて説いているところが、金次郎の心の広さとユニークさを物語っているように思います。難しい言葉で講釈したところで、百姓には伝わらないことをよく理解されていたのでしょうね。
とても大事なポイントとしては。
その田んぼ(自分の心)を耕し、美田にするのは、自分自身であること。
他人にしてもらうのではない、ということであり、
その前提として。
皆が田んぼ(=自分の心)を持っているということを、ちゃんと認識(感謝)すべき、ということ。
田んぼを放置しておいて黄金の稲穂などできるわけなどなく、実りのお米ばかりを求める愚人に凡事徹底を諭すのに最適なたとえではないでしょうか?
こういう一面から、600以上もの疲弊した農村改革を断行できた偉業の真髄がわかるような気がします。 まずは、百姓たちの心田を耕して、未来への成長につなげていったのではないでしょうか?
ただ。金次郎の本当のおしえとしては、
『 自分の田んぼ【だけ】を耕し自分【だけ】豊かになる 我欲を推奨することはない 』
たらいの水
また、もう一つ有名な金次郎の教えとして『たらいの水の話』があります。
水を自分のほうに引き寄せようとすると向こうへ逃げてしまうけれども
相手にあげようと押しやれば自分のほうに戻ってくる。
だから、人に譲らなければいけない。
…というのは、みんなが知るところなんですが。金次郎の七代目子孫の中桐万里子さんが、この話の前段を付加されてさらに深みを含蓄された話になっていきます。
人間は皆 空っぽのたらいのような状態で生まれてくる。
つまり最初は財産も能力も何も持たずに生まれて来る。
そして。
そのたらいに自然やたくさんの人たちが水を満たしてくれる。
その水のありがたさに気づいた人だけが他人にもあげたくなり、
誰かに幸せになってほしいと感じて水を相手のほうに押しやろうとする。
そして、幸せというのは、
自分はもう要りませんと他人に譲ってもまた戻ってくるし、
絶対に自分から離れないものだけれども、
その水を自分のものだと考えたり、
水を満たしてもらうことを当たり前と錯覚して
足りない、足りない、もっともっと、と
かき集めようとすると、幸せが逃げていく
「二宮金次郎の幸福論」致知出版社 中桐万里子著
この「たらいの水」の前段までご存知の方はあまり多くはないかと思います。 二宮尊徳の飾らない人柄がにじみ出るような、シンプルで核心をついた人生訓にただただココロが響きます。