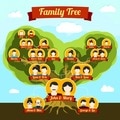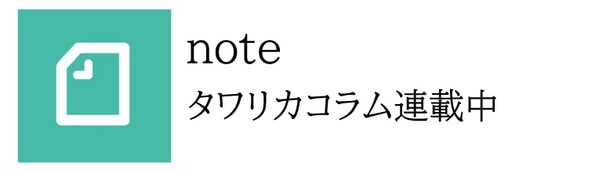永続する企業の条件とは…「たねやの8つの心」「松下幸之助と稲盛和夫」
毎年、新設法人の数は年間10万社を越えているものの、企業の生存率としては、5年後の生存率は平均約20%弱。10年後の生存率は平均約5%前後だそうです。
そして、海外に比べて日本は、100年を超える長寿企業が多いのが特長ですが、100年後に生き残る企業は1000社のうち2、3社。つまり0.2~0.3%!!
それでも、現在でも100年超の企業数は、約25,000社あるといわれています。 有名な世界最古の会社:株式会社金剛組(大阪)の創業は578年ですから、1400年を超える超長寿企業が現存(しかも日本!)していることは本当に驚きです。
では、短命企業と長寿企業の違いは何なのでしょうか?その必須条件をご紹介します。
1.永続する企業の条件
企業という生命体を維持発展させていくために必要な条件を、3000社以上の企業コンサルティングとして実際に携わってこられた佐藤芳直氏(S・Yワークス)が語られました。
「経営者は日々あらゆる判断を迫られます。
この意思決定はどんな未来に繋がるのだろうと考えるとき、3つのフィルターをかけます。
① 継続性・・・ わが社の永続に繋がるか否かということ。その核心は公益性。 ② 安定性・・・ 着実に成長するかということ。 ③ 繁栄性・・・ 利益に繋がるかどうかということ。
|
上記の優先順位で意思決定を行う経営者は、長期的に企業を発展させることができています。
ところが、③⇒ ②⇒ ① つまり、儲かるかどうかを第一に考える企業はいずれ倒産に繋がっているのを数多くみてきました。
起業し、事業が繁栄する経営者はみな、①の公益性の言葉を表現した経営理念を設置していますが、歳月が経ち代替わりしていくと次第に形骸化していきます。
重要なのは、「原点は継承せよ。仕組みは革新せよ。」
原点を継承することが歪んでしまうと、永続性はもとより、決して一人で成し遂げることのできない壮大な志を果たすことはできません。」
また、もう一方。 田中真澄氏(ヒューマンスキル研究所所長)の長年の老舗企業の研究成果から、永続企業に共通する3項目をご紹介します。
永続企業に共通する3項目 ① 確固たる経営理念があること ② 商人の生き方、原理原則というものをしっかり持っていること ③ それを実際に従業員に伝えて「実行させる仕組み」があること |
2.たねや『8つの心』
創業141年の老舗菓子舗「たねや」。今では地元の滋賀・関西にとどまらず、東京にも出店し全国ブランドに成長されました。 和菓子はもとより、クラブハリエのバームクーヘンも有名ですよね。
「三方よし」で有名な近江商人の遺訓や、たねやに代々続く商いの心得をまとめ上げた「末廣正統苑(すえひろしょうとうえん)」 は商道のバイブルといわれているそうです。
その中から毎日終業時に従業員全員で唱和されているという「8つの心」をご紹介します。
たねや『8つの心』
一つ 私は素直な心でいただらうか
二つ 私は人様の無事と倖せを祈る心を忘れはしなかったか
三つ 私は正直と敬う心を持っていただらうか
四つ 私は装う心を大切にしていただらうか
五つ 私は手塩にかける心を忘れてはいなかったか
六つ 私は感謝の心を持っていただらうか
七つ 私は親切の心を大切にしていただらうか
八つ 私は活き活きする前進の心をもっていただらうか
商売や経営の範疇にとどまらず、たとえサラリーマンだろうが主婦だろうが、人の道における心の定義そのもの、だといえると思います。
その商道のバイブルといわれている「末廣正統苑(すえひろしょうとうえん)」からもう一つご紹介いたします。
天平を支へる芯柱(はしら)は
正直の心
感謝の心
能(すす)みて努力するの心
倹約の心
親切
陰徳の行んることを肝に銘じて起つべし
これにて近江の商人の世渡り
商いの実は小さくも世の一隅を照らし得
遂には不滅の灯をかかげ
その道も奥味(おうみ)に達すべし
一部抜粋:「末廣正統苑」

天平とは、近江商人が担いでいた天平棒のことで、それを支えていた心根は、
正直・感謝・努力・倹約・親切・人知れず徳行を積む、ことにほかならないということだそうです。
この短くまとめられた商道の真髄は、近江商人だけではなく、現代においても、通奏低音のように多くの日本人の心の奥底に流れていると思います。 この言葉に心響かない経営者の末路が、企業の寿命結果となっているのかもしれません。
「ダルマの原理」
この心根というのは、「ダルマの原理」と同じです。
ダルマ(達磨)はいくら倒しても必ず起き上がってきますが、その理由は、中に鉄の塊が入っているからです。
そして、その割合というのは、「体:おもり= 8:2」で作られています。
この「おもり」の部分、つまりは「心根」がしっかりしているからこそ、他の物を引っ張って立つ構造になっているんですね。

3.松下幸之助氏と稲盛和夫氏
日本を代表する名経営者リストの上位に挙がるのは、やはり松下幸之助氏や稲盛和夫氏ですが、松下幸之助氏の一言がなければ、現在の稲盛和夫氏ならびに京セラがなかったかもしれない、という話はとても有名ですね。
50年ほど前、関西財界セミナーで松下幸之助氏が「ダム式経営」の必要性について講演されました。「ダム式経営」というのは、水を貯めるダムのように、外部の諸情勢の大きな変化があっても適切にこれに対応し、安定的な発展を遂げていくことができる適正な余裕というものが、設備や資金、在庫、人材、技術、商品開発といった経営のあらゆる面に必要であるということ。
講演中にある出席者が、「ぜひそのダム式経営の方法を聞きたい。」と質問したところ、松下氏は、「まずは、ダムをつくろうと強く思わんといかんですなあ。願い念じることが大事ですわ。」との回答に、会場全体に失笑が広がる中、たった一人、頬を紅潮させて真剣にその言葉を聞いていた若者が、稲盛氏だったそうです。
「いまの自分は経営を上手に進めたいとは思っているけれど、強く願い念ずる、それほどの思いはなかった。強烈な祈りを込めるほどの熱意はなかった。祈り念ずるほどの強烈な思い、強い熱意が出発点なのか!」と。
2人の共通点
松下氏と稲盛氏の共通点は、「利益を事業戦略の原動力にしていない」 ということにあります。では、お2人にとっての、事業の基本的な原動力というのは、
①利益よりもより大きな社会的使命(=社会貢献)
②人間的使命(=従業員の幸福追求)
で、他のどの経営者よりも「凡事徹底」「覿面注意」で従業員を大事に育てていったからこそ、強い組織をつくりあげ、一零細企業を世界で戦うことができる日本の大企業へと成長させることができたといえると思います。
![]()
![]()