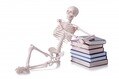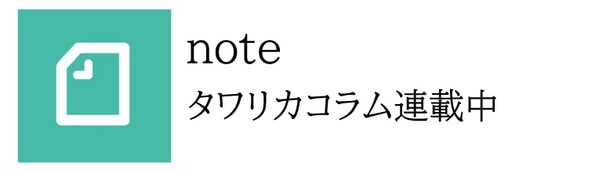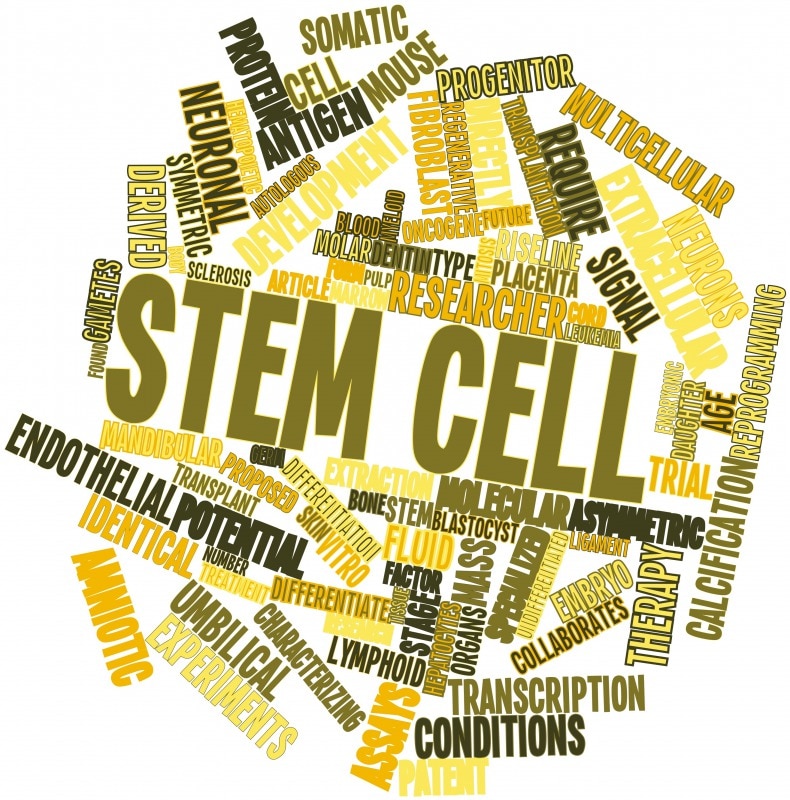
iPS細胞についての最新情報
京都大学でパーキンソン病の患者を対象にした国内初の治験がはじまるなど、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使った再生医療の道がはじまりましたが、まだ課題は少なくありません。
iPS細胞とは
iPS細胞とは…
人間の皮膚などの体細胞に、ごく少数の因子を導入し、培養することによって、様々な組織や臓器の細胞に分化する能力とほぼ無限に増殖する能力をもつ多能性幹細胞に変化します。 この細胞を「人工多能性幹細胞」と呼びます。英語では「induced pluripotent stem cell」と表記しますので頭文字をとって「iPS細胞」と呼ばれています。 名付け親は、世界で初めてiPS細胞の作製に成功した京都大学の山中伸弥教授です。
体細胞が多能性幹細胞に変わることを、専門用語でリプログラミングと言います。 山中教授のグループが見出したわずかな因子でリプログラミングを起こさせる技術は、再現性が高く、また比較的容易であり、幹細胞研究におけるブレイクスルーといえます。京都大学iPS細胞研究所 Cira(サイラ)より
iPS細胞とES細胞との違い
iPS細胞
【作り方】皮膚や血液などの細胞に特殊な遺伝子を入れる
【特 徴】どんな細胞からも作製可能
【課 題】作製に時間・費用がかかる・がん化のおそれ
ES細胞
【作り方】受精卵から細胞を取り出して培養する
【特 徴】品質が安定・海外で研究が先行
【課 題】受精卵を使うことの論理的な問題
iPS細胞は、心臓や神経などの様々な細胞に変化できるため、重い心臓病や脊髄損傷などを治すのに役立つと期待されています。同じように変化できる細胞としては「ES細胞(胚性幹細胞)」もあり、海外ではES細胞の方が数多く研究されています。
ただ、ES細胞は、赤ちゃんに育つ前の受精卵を壊してそこから細胞を取り出して作るため、その作り方をめぐる倫理的な課題があります。加えて、ES細胞はもともと患者本人の細胞ではないため、ES細胞から様々な細胞を作って移植しても、そのままでは患者の免疫システムが「異物」とみなして攻撃してしまうことがあり、こうした反応は免疫拒絶反応とよばれ、この反応を抑える薬が必要になります。
これに対し、iPS細胞は、皮膚や血液などのあらゆる細胞から作ることができるため、倫理的な課題はクリアでき、患者自身の細胞を使えば、拒絶反応もおこりません。
万能だがコスト高
しかい、患者自身の細胞からiPS細胞を作るには、半年~1年かかり、コストも最大1億円近くに上るという。これでは、実際の治療に使うのには難しい、という課題が残ります。
そこで、京都大iPS細胞研究所では、拒絶反応が起こりにく特殊な免疫タイプの人の細胞から、あらかじめiPS細胞を作っておく計画を進めていて、2020年度には、日本人の50%に対応できる種類の細胞がそろう見通しとのこと。
まだまだある課題
iPS細胞を使った治療を広げていくには、「がん化」にも注意が必要。「品質」が悪いとガン化する恐れがあるからです。このため、人を対象にした研究では品質の良い細胞を選んで使い、万が一に備え、がんができていなかどうかを慎重に調べていく方針。
実用化に備えてiPS細胞を特定の病気の細胞に変化させて病気を再現し、効く薬を探す「創薬研究」も行われはじめました。筋肉の中に骨ができる難病などで薬の候補が見つかり、効果を確かめる治験が、国内ではじまっています。
再生医療市場急拡大
iPS細胞やES細胞でなく、患者自身や他人の細胞を取り出し、培養するなどしてから移植する再生医療はすでに実用化しています。
日本では患者の細胞を培養した軟骨など4件が「再生医療等製品」として使用が承認されました。
世界の再生医療市場は急速に広がっており、経済産業省の2013年の試算によると50年に53兆円(製品・加工品は38兆円、周辺産業は15兆円)急成長すると予測されています。
日本も実用化を加速するため、再生医療製品の早期承認制度を14年に導入。最短でも6年ほどかかる製品化の手続きを2~4年前後に短縮できるようにしました。
(2018年11月10日 読売新聞)