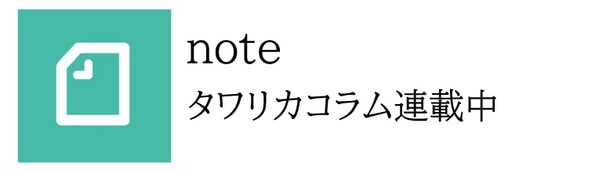【ココロ】との上手なつきあい方|イライラをコントロールするテクニック
ついつい、イライラや怒りの感情を抑えきれず、自己嫌悪に陥った経験は誰にでもあるのではないでしょうか?
「ココロ」と上手につきあう方法を身につけておけば、仕事や家庭、学校などで周囲の人たちとの関係づくりにも活かすことができます。メンタルヘルス改善を目的に、イライラや怒りの感情をうまくコントロールする「アンガ―マネジメント」についてご紹介します。
1. イライラや怒りの発生する原因
●怒るという感情は、突然起こるわけではない
私たちは、イライラや怒りの感情を爆発させてしまったために、人間関係を悪化させてしまったり、信頼を失ってしまったりすることがあります。
一般に、怒ることは悪いことだと思われがちですが、実は、自分を守る防衛感情です。自尊心や名誉、価値観を守るために怒るため、本能的にもとても自然な感情なので無くすことはできません。
怒りは「第二次感情」といわれ、その前段階にあるのが、「第一次感情」でといわれる、嬉しい・楽しい・つらい・悲しいといった感情です。この第一次感情のうち、つらい・苦しい・悲しい・不安といったネガティブな感情がいっぱいになると、心の中にある感情のコップから水があふれだすように、怒りという第二次感情に形を変えて表れます。
怒りっぽい人は、心のコップが小さい人といえますが、怒りは、アレルギー反応とよく似ています。同じ出来事が起こっても、怒りの反応が出る人もいれば、出ない人もいたり、また、イライラを感じる日と感じない日があるのは、コップの中の量が関係しています。
●怒りが発生するメカニズム
怒りをコントロールするには、怒りの感情がどのように生じるかを理解しておく必要があります。
「怒り」が発生するメカニズム STEP1 : 出来事が起こる 【ex:電車の中でお年寄りに足を踏まれた】 STEP2 : 出来事の意味づけ
*意味づけA… 「わざと踏んだのか?」「足を踏んだのならきちんとあやまるべき」と考える。 *意味づけB… 「電車が揺れてよろけたのか?」「大丈夫だろうか」と心配したり、いたわりの心をもつ。 STEP3 : 思考・感情の発生 【意味づけAのように考えると、怒りの感情が発生するが、意味づけBでは発生しない。】 |
怒りが発生するまでの3段階のうち、ポイントとなるのがSTEP2 の意味づけです。
怒りの原因は、出来事そのものではなく、出来事に対してネガティブな意味づけを行う自分自身の思考パターンにあることに気づくことが重要なのです。
2.アンガ―マネジメントとは

アンガ―マネジメントとは、1970年代にアメリカで生まれたとされる心理教育・心理トレーニング法です。
多くの人は、怒ってしまったことを後悔しますが、その一方で、うまく怒れないことに悩む人もいます。特に、日本では我慢が美徳とされていますが、これは裏を返せば、怒りを表現するのが下手ということができます。
アンガ―マネジメントは、怒らない方法、イライラしなくなる方法ではなく、感情に振り回されて後悔しないためにも、無駄に怒らず、怒りの感情と上手につきあうことを目指しています。
3.「ココロの筋トレ」がおすすめ!
●イライラや怒りの強さを10段階に分けてみる
怒りの感情を「怒っている」と「怒ってない」という2つの感情に分類しがちですが、この2つに大別すると、多くの出来事が「怒ってる」方に分類されてしまいます。
実際には、怒りの度合いは幅広いので、怒りの強さを10段階にわけてみましょう。
過去にこれほど怒ったことはない、というような強い怒りを10として、ほとんど怒りを感じない状態を0~1にするなど、怒りのレベルを自分で設定してみてください。
そして、イライラや怒りを感じる出来事があったら、「これはレベル3だから大した怒りではない」などと、レベル別に分類します。 このように、自分の行動を客観視して数値化することで、イライラや怒りを鎮める効果があるのです。
10 |
最大級の怒り |
ふるえが止まらないほどの激しい怒り |
逆鱗に触れる・烈火のごとく・はらわたが煮えくり返る・怒り狂う・業を煮やす・腹の虫がおさまらない |
9~7 |
爆発寸前の怒り |
思わず我を忘れそうになるほどの爆発寸前の怒り |
激昂する・逆上する・堪忍袋の緒が切れる・怒りを爆発させる・怒鳴る・語気を荒げる |
6~4 |
腹が立つ怒り |
怒りは全面には出ていないが、相当イライラしたり、怒りを感じたりしている |
頭に血が上る・呆れる・しゃくに障る・腹に据えかねる・息巻く・青筋を立てる |
3~2 |
不愉快な怒り |
イラッとしたり、不愉快に思ったりしている |
カッとなる・むしゃくしゃする・不機嫌になる・顔色を変える・怒りがこみ上げる |
1~0 |
穏やかな怒り |
ストレスをほとんど感じていない状態 |
イラッとする・ムッとする・カチンとくる・腹が立つ・頭にくる・不信感を募らせる |
●「6秒ルール」をココロに命じて
今この瞬間に感じているイライラや怒りを抑える方法としては、すぐに反射しないことが肝心。
怒りの感情のピークは、6秒といわれていますので、この6秒間に「怒りをおさめるための魔法の言葉」を自分に向かってつぶやきながらココロを落ち着けるようにすると、怒りのピークが過ぎて、冷静に対処できるようになり、暴言や相手を傷つけるような行動などの、取り返しのつかない言動を回避することができ、相手との人間関係が悪くなることを防げます。
魔法の言葉は、なんでも構いません。「大丈夫」「落ち着け」「どうってことない」「なんとかなる」などのポジティブな言葉を選ぶのがポイント。あるいは、恋人や子ども、ペットの名前などもココロを落ち着けるための魔法の言葉にはとても有効です。
4.ココロの許容範囲を広げることが大切
●許せないときはきちんと怒る
人にはそれぞれ「許せる範囲」と「まあ許せる範囲」と「許せない範囲」の心の領域があります。
この中で「まあ許せる範囲」を広げることが肝心。相手に対して「~すべき」と思う自分の価値観を見直して、心の許容範囲を広げることで、怒りをコントロールしていきましょう。
それでも、「許せない」という出来事が起こったらどうしたらいいのでしょうか?
そうした場合には、怒りの感情を抑え込みすぎずに、怒るべきときにはきちんと怒っていいのです。感情にまかせて相手に怒りをぶつけるのではなく、怒るべきときに、怒りの感情を上手に表現することがアンガ―マネジメントの目指すところです。
●怒るべきことかどうかをきちんと判断する
今、起こっているいる出来事は、本当に怒るべきことなのか、スルーできるものではないのかを分析します。 判断基準となるのは、「自分にとって重要か、重要ではないか」「自分が行動することで状況を変えられるか、変えられないか」の2つです。
*自分にとって重要で、変えることできるもの
→上手に怒って意思表示をする。(ex:ミスを繰り返す部下に上司として怒っている事を表示)
*自分にとって重要だが、変えられないもの
→受け入れるしかない。(ex:急いで取引先に向かっている時に渋滞に巻き込まれた場合)
*自分にとって重要ではないが、変えることができるもの
→余裕のある時に対応する。(ex: 超多忙な時に取引先から愚痴のようなメールが届いた場合)
*自分にとって重要ではないが、変えられないもの
→放っておく。(ex:電車の中でマナーの悪い人がいた、車の列に割り込んだ人がいた)