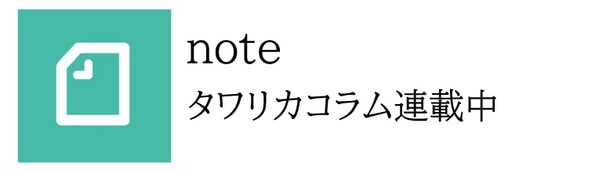着物の裏地のような人間の美しさ|見えないところが美しい人間であれ
清々しい新年をお迎えのことと存じます。一年の計は元旦にありということで、ワタクシもしっかりと毎年恒例の元日の書初めをすませました。
インナーケアラボとしては、2018年もやはりココロ磨きを基に、美腸活に関する大事なことをお伝えしていきたいと思います。
1.母として。そして彼女の少し前を生きる人生の先輩として。
私にも娘がおります。これからを生きる子どもには、ぜひ「生きぬく力」を身につけてほしいと思っています。
木にたとえるならば、葉の色や形を整えることだけに意識を向けるのではなく、もっと幹や根の部分をしっかりと太く育って欲しい、と心から願います。
それは、人として【心根】を育てること。
根がしっかりと育っていれば、すぐに倒れることもなく、青々とした美しい葉が育つから。
元気に育ったらいい、っていうだけなのもやっぱり無責任だと思うし、かといって偏差値にこだわりすぎるのも狭量な人間だな、と呆れてしまう。
ただ、やはり、日頃から心がけているのは、【善悪の判断=モノサシ】だけは、しっかりと教えてやりたい、と思っています。
行動判断の基準を「損得」ではなく、「善悪」にするととても楽。その時は一瞬損したかのように思っても、後から「善」にchangeするから不思議です。
そんな私の心の琴線に、ビビっと響いた言葉に出会いました。
750年の歴史を持つ博多祇園山笠の人形師歴65年の名工 三宅隆氏(1935年生)の言葉です。
『個性を大切にと言うけれど、
技術の基礎ができていない者に、表現できる個性などない。
仕上げの善し悪しより、人形の内側からの力が人を惹きつける山笠の人形は、
勇ましい迫力とともに、品がないといけない。』
三宅 隆氏
これは、職業としての人形師だけに限らず、人間としても言い得てることで、このようにすぱっと言いきれる素晴らしい言葉を前にして、三宅氏の長い苦労と筆舌に尽くせぬ努力が垣間見れたような気がしました。
娘のまなざしを鞭として、しっかりしなきゃ!と自分自身を発奮させながら、少しでも彼女の道標となるような女性を目指して心眼を磨いていかねば、と思います。
2.着物の裏地のような人間の美しさ
詩に曰く、錦を衣て絧を尚うと。其の文の著わるるを悪むなり。
故に君子の道は闇然として日に章らかに、小人の道は的然として日に亡ぶ。
中庸の中の「詩経」という書物に書かれてある言葉を挙げて、例えているのですが
つまり。「めざすべきは、着物の裏地のような人間の美しさである、」ということを意味しています。
外側は無地で控えめな着物を衣て、中には美しい模様が施されている長襦袢を衣るように、「見えないところ」が美しい人間であれ、とのこと。
人間を磨くということは、外面を飾り誇るのではなく、人目に触れない内面を磨き高めていくことにほかならない、ということを指しています。まさにインナーケアラボの真髄の言葉ですので、ご紹介させていただきました。
2018年が皆さまにとってどうぞよい年になりますように。本年もどうぞよろしくお願いいたします。(所信表明の書初めも掲載させていただきます。)
![]()